……その帝国では地図作成法の技術が完璧の域に達したので、ひとつの州の地図がひとつの市の大きさとなり、帝国全体の地図はひとつの州全体の大きさを占めた。時のたつうちに、こうした厖大な地図でも不満となってきて、地図作成法の学派がこぞってつくりあげた帝国の地図は、帝国そのものと同じ大きさになり、細部ひとつひとつにいたるまで帝国と一致するにいたった。地図作成にそれほど身を入れなくなったのちの世代は、この膨張した地図が無用だと考え、不敬にも、それを太陽と冬のきびしさにさらしてしまった。西部の砂漠地帯にはこの地図の残骸が断片的に残っており、そこに動物たちや乞食たちが住んでいる。これ以外、国中には地図作成法のいかなる痕跡も残されていない。
スアレス・ミランダ『周到な男たちの旅』第四書十四章(レリダ、一六五八)
はじめに: 地図と領土
「地図と領土」といえばミシェル・ウエルベックの小説である。孤独な芸術家ジェドが世捨て人の作家ウエルベックと出会う物語だが、このタイトルは言語学者コージブスキーの「地図は領土ではない(A map is not a territory)」という言葉が元になっている。
これが意味するところは、一見すると自明であるように見える。記録映像が出来事そのものではないように、地図は領土そのものではない。そうではないだろうか。
だが実際のところ、事態はそれほど単純ではない。語とその表現対象がつねに容易に区別できるとは限らないからだ。たとえば、多くの人は「ほんものの数字の3」と「3という記号」を区別して考えてはいないだろう1。
マグリット「イメージの裏切り」は、言葉の使用において起きうるこのような混乱をよく表現している。たいへん有名な絵2だが、描かれたパイプの下に
「Ceci n’est pas une pipe.(これはパイプではない)」
という一文が添えてある。一見すると矛盾とも思えるが、よく考えてみればこれは絵だから、パイプそのものでないのは明らかだ。標語的に言えば「パイプの絵はパイプではない」のだ。
マグリット本人はこの絵について以下のように説明している。
有名なパイプだ。これのせいで人々にどれほど非難されただろうか!
でも、私のパイプにタバコを詰めることはできるかな? いいや、これは単なる絵画表現に過ぎない、そうだろう? だから、もし私が絵に「これはパイプだ」と書きこんでいたら、私は嘘をついたことになったはずだ!3The famous pipe. How people reproached me for it! And yet, could you stuff my pipe? No, it’s just a representation, is it not? So if I had written on my picture “This is a pipe”, I’d have been lying!
Torczyner, Harry. Magritte: Ideas and Images.
マグリットはこの類の、言葉の性質に切り込んだ絵を多く描いている。
たとえば「ことばの用法」では、なんとなく人型をとった白い不定形の各部に「木」「大砲」「女の身体」という字が書き込まれている。これは標語的に言うと「地図さえあれば、領土はなくてもよい」ことを意味している4。マグリットの慧眼と言っていいだろう。
縮尺1/1の地図
World map by Gerard van Schagen, Amsterdam, 1689 (Public Domain)
地図は一般には領土ではないが、現実に迫るほど精巧な地図についてはどうだろうか。縮尺1/500や1/250の地図であればかなり詳細だと言えるだろうが、それらでさえ現実世界のもつ情報量にはとうてい及ばない。
では、仮に縮尺1/1の地図であればどうだろう? 人間や動物の1/1サイズ模型ならまだしも、1/1の縮尺の地図というのはそれが示す領土と大きさが一致してしまい、まあ端的に言って「領土に置けない」わけだが、想像はできる5。
この分野についての先駆者はボルヘスである。ボルヘスは自著で「学問の厳密さについて」という小話を紹介していて、6それはこの記事の冒頭に掲げてある。ある帝国では地図学の発展とともに地図の縮尺がどんどん大きくなっていき、やがてそれは国全体と正確に一致するようになるが、地図学の衰退するにつれて打ち捨てられてしまうという話だ。
ここで先ほど提示した問題にもどろう。縮尺1/1の地図は、領土であるといえるだろうか? もちろん物質として領土そのものでないのは明らかなのだが、それは領土の情報を余すところなく完璧に含んでいると言えるだろうか。
ウンベルト・エーコが検討7したところによると、そうではない。いわく、仮に1/1の地図が領土に重ねて置かれたとすると、その地図はすでに不正確である。なぜならその地図は、「領土が地図に覆われている」ことを表現できないからだ。「領土に地図が置かれていることを表す地図」を用意してもけっきょくは同じ問題が起き、この「地図の地図」の連鎖は果てしなく続くように思われる。無限後退に陥るというわけだ。
エーコは<標準地図>8なるものを用意してこの連鎖を止めようとするが、けっきょくそれは不可能であるという結論に至る。縮尺が極限にいたった地図でさえ、領土であるとはいえないのだ。
余談だが、エーコはここでラッセルのパラドックスを持ち出している。この箇所は一般には
地図もまた領土の一部をなす以上、帝国全体と完全に一致した地図を構想することは、自己言及のパラドクス(ラッセルのパラドクス)に陥らざるをえない
地図のメランコリー 地図制作(マッピング)の喪 | 田中純
などと解説されるが、わたしは必ずしも賛同しない。エーコ本人の書きぶりはかなり曖昧だし、すべての自己言及がただちにパラドクスを引き起こすわけではない910からだ。
クワイン
現代の経験主義は、ふたつのドグマによって大きく条件づけられてきた。ひとつは、分析的な真理、すなわち事実問題とは無関係に意味に基づく真理と、総合的な真理、すなわち事実に基づく真理との間に、ある根本的分裂があるという信念である。もうひとつのドグマは、還元主義、すなわち、有意味な言明はどれも、直接的経験を指示する名辞からの論理的構成物と同値であるという信念である。どちらのドグマにも根拠がないと私は論ずる。これらのドグマを捨て去ることのひとつの結果は、あとで見るように、思弁的形而上学と自然科学とのあいだにあると考えられてきた境界がぼやけてくることである。もうひとつの結果は、プラグマティズムへの方向転換である。
W.V.O.クワイン「論理的観点から」
少し話を変えよう。クワインについての話だ。
単にクワインといえば哲学者 W. V. O. クワインを指すが、プログラミングの文脈におけるクワインとは、「自身のソースコードと完全に同じ文字列を出力するプログラム11」のことだ。
ここではクワインの具体的な実装を云々することは避けるが、それが何を実現すると言っているのかについて簡単に説明しておこう。Pythonでも何でもいいが、適当なプログラミング言語を考える。そこで
print("Hello World!")なるソースコードを実行すると「Hello World!」が出力されるとしよう。
このとき、「Hello World!」という文字データはソースコードに書かれたそのまま出力されているが、その周りの「print(” “)」という操作の部分は出力されない。
この例は、多くのプログラミング言語ではデータ部と操作部が区別されるという事実を簡潔に示している。データには種々の操作をほどこすことができ、またそれは出力されて外部にあらわれるが、操作部はプログラムの処理を表すためにあって、出力結果にはあらわれない。
この区別を超えて「操作部も含めて自分自身とまったく同じコードを出力しますよ」と謳っているコードがクワインである。クワインを書くことの(ちょっとした)難しさが伝わっただろうか。鉛筆を使って絵と鉛筆を作れと言われているようなものである。実世界では、このような行いはなかなか難しいだろう。
ではなぜプログラミングにおいてクワインが成立するのかというと、プログラムのソースコードにおいては、命令部もデータ部も同じような文字(アルファベットや数字、記号)から出来ており、ある意味均質に扱えるからだ12。
クワインは、プログラミングにおいて、実体としての出力とそのための道具の区別がかなり曖昧になりうることを示している。これは意図的な混同だと言われてしまうかもしれないのだが、おもしろい部分だとぼくは思っている。ブルックスがソフトウェア開発の名著「人月の神話」で
プログラマは、詩人と同様に、純粋な思考物からほんの少ししか離れていないところで仕事をする。
ブルックス「人月の神話」第1章 タールの沼
と述べた気持ちもわかる。
広く捉えれば、クワインは縮尺1/1の地図を仮想的に実現したものだと考えられないだろうか。実体としてのデータと、それを表現するための道具立てが一致しているからだ。現実世界ではエーコの言うような制約をこうむる縮尺1/1の地図は、コンピュータの世界ではある程度実現される。
modelの問題
Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable.
シンプルなものは常に誤っている。そうでないものは使い物にならない。
ポール・ヴァレリー
さて、ルイス・キャロルの作品「シルヴィーとブルーノ」にも、縮尺1/1の地図についての言及がある。
それどころかこの作品の登場人物たちは、縮尺1/1の地図にさえ飽き足らず、百尺竿頭に一歩を進んでその先へとたどり着いた。領土そのものを地図として使うのだ。
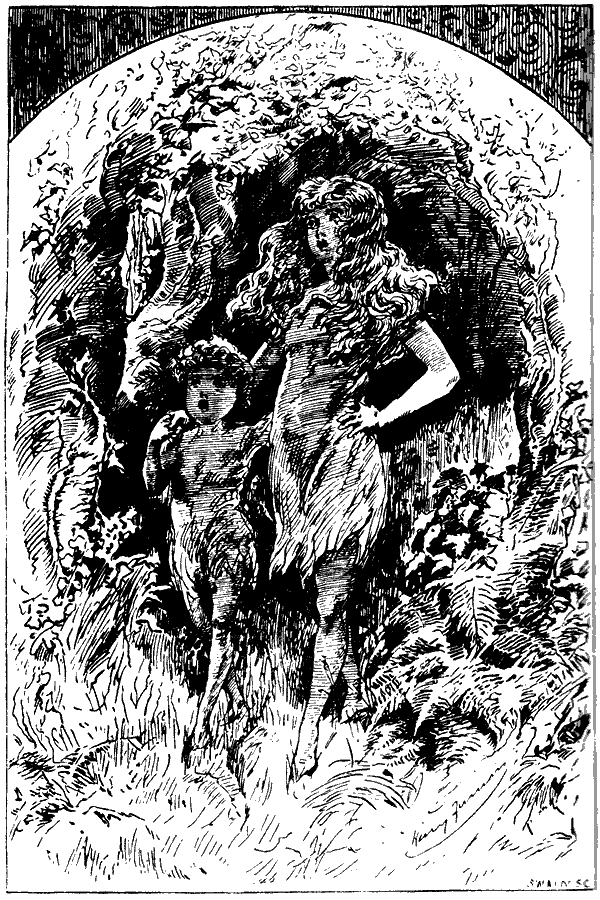
「そいつは君たちの国からわれわれが学んだもうひとつのことだ」とマイン・ヘルは言った。「地図作りだよ。けれど、われわれは君たちよりももっと先まで進んでいった。実際に役に立つ最も大きな地図ってどのくらいだと思うかい?」
「およそ一マイルにつき六インチといったところでしょうか。」「たった六インチだって!」とマイン・ヘルは叫んだ。「われわれはすぐに一マイルにつき六ヤードに達した。そして、一マイルにつき百ヤードを試してみた。それから、もっとも偉大なアイディアに辿り着いたんだ! われわれは国土の地図を、一マイルにつき一マイルの縮尺で作ったのだよ!」
「それをよくお使いになりましたか?」と私は尋ねた。
「そいつはまだ拡げられておらん」とマイン・ヘルは言った。「農民たちが反対したんだ。そいつが国土全体を覆い、日光を遮ってしまうだろうとね! それでわれわれは今では国土そのものをそれ自体の地図として使っている。保証するが、結構それで間に合うよ……(後略)
ルイス・キャロル「シルヴィーとブルーノ」
ここにおいては、対象とそのモデルが一致してしまっている。説明するのも野暮だがこれは顛倒した態度であって、「砲弾の軌道を予測するために物理学を使わなくても、実際に撃ってみればいいじゃないか? 」と言っているようなものだ。あるいはこういう主張だと思ってもよい。「砲弾を撃つことそのものが計算だ」と。
「地図と領土」関係は、このように、モデルの適切な複雑さに関するものだと考えることもできる。精巧を極めたモデルは、実物そのものと一致し、ついには消滅してしまう。実用的なモデルは適度な粗さを保つ必要があるのだ。
円城塔は、小説「Self-Reference Engine」の中でこの「モデルと実物の一致」という発想を取り扱っている。この小説には「巨大知性体」なるコンピューターの成れの果てのような存在が登場するのだが、その基本的なコンセプトは、計算を自然現象と同一視するというものだ。
なぜ自然現象を模範にとるのかというと、計算速度の極限がそこにはあるからだ。一般に人間の考えるような計算にはステップが存在し、その各ステップは有限の位置を占めるから、無限に速い計算というのは考えがたい。しかし、仮に計算過程のない計算が存在すれば、その速度には限りがなくなるだろう。
作中では、とある神父Cがこれを提唱する。
「そういった過程はしかし、存在する」
円城塔「Self-Reference ENGINE」05: Event
子供のような無邪気さで告げたのは、当時最大の電子頭脳規模を誇った神父Cだった。
「自然現象はまさにそのような計算として今この瞬間も進行している」
そして、その帰結はこうだ。
もしもこの世が義脳の中にあるとするならば、義脳が認識する義脳自身のクロック数が世界で最速の計算となる。義脳の中で行われる計算などは、電子頭脳の中に組み上げられた電子頭脳で計算を行うようなもので、ただの二度手間であるにすぎない。計算機なるものが自然の中で行っているのはそういう種類の二度手間である。
結局のところ、自然現象を超える計算速度は存在しない。
今は神父Cのテーゼとして知られている。
ならば、自然現象として計算を行えばよいではないか。その、意味すらよく掴めない計画を真っ正直に受け止め、そして実現へと進めていったのは、人間ではなく当時各国で建設の始められていた巨大知性体群だった。
彼らは素朴な大容量義脳として想像を絶して素朴であったため、自然現象とは計算ではないし、われわれも仮想空間の中に暮らしているわけではないという意見などは一切顧慮しなかった。仮想空間の中で石を落としてその挙動を予測するよりも、自然界で石を落としたほうが余程手軽で早い。環境という擾乱により、正確さが多少犠牲になりはするが、それは技術的に解決可能な問題である。その前提だけを出発点に、巨大知性体群は前人未踏で後人未踏などこかの土地へ辿り着いた。「そしてわたしたちはそよ風になった」
円城塔「Self-Reference ENGINE」05: Event
……(後略)
これは現実世界におけるチャーチ・チューリングの提唱に対する、円城塔なりの乗り越えであることは明らかだろう13。
チャーチ・チューリングの提唱とは、以下の主張だ。
《Church-Turing の提唱》計算可能であるとは、Turing機械で計算可能であるということである。14
Turing機械とは無限の長さのテープに対してヘッドで読み書きをして計算を遂行する仮想的な機械だ。多くのプログラミング言語はTuring完全(Turing機械と同等の計算能力を持つ)だから、つまりはふつうのコンピュータと同等の計算ができる15数学的な仮想機械だと思ってもらえればよい。
チャーチ・チューリングの提唱は、数学者や計算機科学者にかなり広く受け入れられてはいるが、ただしいことが証明できる性質のものではない。「計算可能である」という漠然とした概念を定義する提唱にすぎないのだ。
提唱にまつわるこのような事情は、計算という漠然とした概念に対して人間の分析がまだ不十分であることを意味していると受け取れる。これをもう少しポジティブに見れば、この提唱はTuring機械よりも何らかの意味で高い計算能力を持つモデルが存在する可能性を排除していないのだ、という点に着目することもできるだろう16。
いま我々が、自然現象とTuring機械というふたつのモデルの間に立っているとしたら、われわれはどこまで自然現象に近づけるのだろうか。
シミュレーションへ

今後、地図こそ領土に先行する――シミュラークルの先行――地図そのものが領土を生み出すのであり、仮に、あえて先のおとぎ話の続きを語るなら、いま広大な地図の上でゆっくりと腐敗しつづける残骸、それが領土なのだ。帝国の砂漠にあらずわれわれ自身の砂漠に点在する遺物とは、地図ではなく実在だ。実在の砂漠それ自体だ。
ボードリヤール「シミュラークルとシミュレーション」
最後にボードリヤールを見てこの記事を締めくくろう。ボードリヤールは「シミュラークルとシミュレーション」において、ボルヘスの挿話を引用して、それを逆転させている。「縮尺1/1の地図」はあくまで領土を前提としていて、それにどこまで近づけるかという試みだったが、ボードリヤールはそれすら「シミュラークル第二段階のひそやかな魅力でしかない17」と言ってのける。彼の考えによれば、事態はボルヘスの小話からさらに進展し、領土はシミュレーションによって消滅するからだ。
シミュラークルとその3つの段階
ボードリヤールの語り口は多くのフランス現代思想家と同様に晦渋で、そこが味でもあるのだが、ここでは「シミュラークル」と「シミュレーション」に的を絞ってシンプルに説明しよう。
「シミュラークル」はフランス語で虚像、イメージを意味する語だが、ボードリヤールの使い方としては「ある時代における現実の記号化の図式」を意味していると思えばよい。ボードリヤールは、シミュラークルを大きく3つの段階に分類した。
- 「模造」の図式
- 「生産」の図式
- 「シミュレーション」の図式
「模造」の図式 ――自然的価値法則――
第1の図式はルネッサンスから産業革命までの間に見られたもので、封建的秩序の解体によって誕生した。ブルジョワ的秩序の誕生によって、人々が記号をある程度自由に使えるようになったからだ。

これはどういうことか。まずカーストや身分制度の厳しい世界には、流行が存在しない。記号の数や、誰がそれを使ってよいのかについては厳しい制限があるからだ。その記号とはたとえば、王だけが身にまとう衣装であり、秘密の儀式であり、貴族だけが持てる趣味だ。また、誤った記号の使用は罰せられる。
しかし、それらの社会制度が解体された後のブルジョワ社会は流動的である。そうなると記号の自由な流通がはじまり、流行が生まれ、また記号の差異をめぐる競争がはじまる。いまの社会にも見られる、白いTシャツに「supreme」のロゴが印刷されているかをめぐる競争を想像してもらえればいいだろう。
一部の人間が確実な記号を保有していた封建的秩序とは異なり、第1のシミュラークルのもとでは、大量の人が記号を利用する。その需要を満たすために何が行われるかというと、「模造」がはじまる。明白さ、自然さによって支えられた記号とはことなる、ある意味では偽物の記号が生まれる段階だ。
ボードリヤールはこのような模造の好例としてバロック芸術における「漆喰(スタッコ)」を取り上げている。漆喰はビロードのカーテンから木の軒蛇腹、人間の体の丸みまで、あらゆるものを模倣できる。素材がごちゃまぜであった時代から、ただ一つの新しい物質へ。記号の独占は打ち破られ、シミュラークルは次の図式へとなだれ込んでゆく。
「生産」の図式――商品の価値法則――
第二の図式は、産業革命と共に到来する。記号はカースト的伝統と無縁になり、大量にあふれるようになったのだ。
記号という言葉を使わなくてもよければ、つまりは、モノが大量生産されるようになった。そして、それらn個のモノの間には、「オリジナルと複製」といったような関係はもはや存在しない。スーパーマーケットに並ぶキャンベルのトマトスープ缶のうち、どれかが本物であとは偽物だということがあるだろうか18? 大量生産されたもの同士は等価であり、差異は消滅している。準拠枠が、そこにはもうないのである。
この領域は、それはそれで驚くべき事態ではあるが、ボードリヤールに言わせればあくまで過渡的なものにすぎない。
この種の複製の生産は、なるほど「自然らしさ」の領域にたいする挑戦ではあるが、所詮「二流の」シミュラークルにすぎず、世界を支配するにはいささかお粗末な、想像上の解法なのだ。模造と分身、鏡と劇場、仮面と外観の遊びの時代に比べれば、技術と大量生産による複製の時代は、まったく底の浅い時代である。
ボードリヤール「象徴交換と死」Ⅳ 産業段階のシミュラークル
つまりは、第一のシミュラークルにあった演劇的な要素、こう言ってよければ「味わい」「風情」のようなものが第二のシミュラークルにおいては失われているのだ。
ボードリヤールはこれを「自動人形(オートマタ)」と「ロボット」の違いに例えて説明している。


ここでいうオートマタとは、日本でいうからくり人形のようなものだと思ってもらえばよい。19世紀ごろまでの、ぜんまいばねなどを動力として楽器を演奏したり手紙を書いたり、人々を楽しませる機械人形のことだ。
オートマタは演劇的な見た目をもって作成され、魂がないことを除いては限りなく人間に近づく。模倣は常に不吉さをはらむものだが、自動人形はそれでもなお楽天的な存在であり続ける。彼らは演劇的な要素を多分に持っていて、愛らしい存在だ。
しかしオートマタの後に登場する「ロボット」はちがう。ロボットの目的は人間に近づくことではなく、労働だ。それはその命名からも明らかである19。この性質のどこが問題になってくるかというと、要するにロボットは人間の労働者と等価になるのだ。しかも、労働の面においてのみの等価物である。これが人間の労働者にとってどのような――非人間的な――状況をもたらすかは、言うまでもないだろう。
シミュレーションの図式――構造的価値法則――
数学的精神の持ち主であったライプニッツは、0と1とがつくりだす二元的なシステムがもっている神秘的な優美さのなかに、天地創造のイメージを見ている。この二元的機能を無の空間において働かせる宇宙の究極的存在さえあれば、それだけで無からあらゆる存在がつくりだされるのに十分である、と彼は感じたのである。
マクルーハン「人間拡張の原理」
いよいよ第三の図式だ。ボードリヤールの語り口はここに至っていよいよ難解になってくる。
さて、シミュレーションとは何だろうか。一口にいうと「基底となる現実が消え失せ、記号の差異のみが問題になる状態」と説明できるのではないかと思う。以下でこのことを詳しく見よう。
まず前半の「現実の消滅」についてだが、これについてあれこれ述べる必要は実際のところない。単に、現代人の生活を思い浮かべればよいからだ。たとえば労働においては、給与水準は業界の慣行によってきまっていて、生み出すものの価値や本人の優秀さとはあまり関係がない。また、デリバティブなどの高度な金融商品の取引は実体経済ともはや関係があるように思われない。日々のニュースに関しても、一般人のレベルで事件の真相を確かめることは不可能に近く、ときにはフェイクニュースを信じ込まされることもある。
このように、現実への準拠が消滅してコードに支配される世界の例としてイメージしやすいのは、映画「マトリックス」だ20。「マトリックス」において主人公ネオがはじめ現実だと思っていたものは、緑色のコードによって記述され、物理法則も通行人の顔も自由に変更が可能である、シミュレーションされた世界にすぎなかった。
核兵器もシミュレーションの最良の例のひとつである。それは破壊の記号として流通しているだけで、実際に使われることはない。
次に、記号の差異について。ボードリヤールはこれを「DNA」や、コンピュータの動作原理として用いられるような「0/1のコード」にたとえて説明している。シミュレーションにおいて問題となるのはモノのオリジナル性や起源ではなく相対的な差異であり、そして、0と1からなるバイナリ列やATGCの塩基配列によるコードは差異のミニマルなかたちであるからだ。これらのコードは、あらゆる問いと答えをその中に内包していながら、人間には容易には解読できない線条的な信号である21。
このようなシミュレーションの二進的傾向が政治に反映されたものが、たとえば、選挙であり世論調査、国民投票である。これらは本来複雑であるはずの社会的営為を、YESかNOかの問いによってひとつの答えに収縮させてしまう。こうなれば、もはや世論が現実の人々となんの関係もないことは明らかである。世論調査の結果を信じているのは政治家だけだし、政党はもはや何も代表しない。二大政党制を例にとれば、それぞれの党のあらゆる言説は互いに交換可能である。ドナルド・トランプが民主党から立候補するのも不可能ではなかっただろう。
ボードリヤールは以上のような、現代がシミュレーションの図式に従っているという洞察をもとにして、現代社会の諸問題を論じている。地図と領土の話からはだいぶ脱線してしまったが、無理やり話を戻すと、ボードリヤールが言っているのは以下のようなことだ。「地図と領土」が含意するのがモデルと実体の関係だとすると、現代において実体は消えうせているから、そこにはモデルしかないのだと。
おわりに: 双子の塔

ボードリヤールはこれらの議論をさらに押し進め、洗剤会社から東西冷戦の構造に至るまで、すべての支配システムは永続したければ二元支配の形態を取らなくてはならないと主張する。更に、それが建築の姿をとってあらわれたのが、世界貿易センタービルのツインタワーだというのだ。高さに関する競争や起源についての主張は終わり、双生児の塔は周りのビルと争うこともなくただ互いに見つめ合うだけなのだ、と。
この2本のタワーが2001年にどのような運命をたどったかについては、もはや説明する必要もないと思う。このブログでも以前に少し触れたことがある。あまり品のいい言い方ではないが、彼が9/11以前からツインタワーについて論じていたのは、思想家としての引きの強さを感じずにはおれない。
ボードリヤールは9/11の発生直後からこの出来事について盛んに意見を発表しており、このテロがグローバリゼーションから現れてきたのだということを次のように要約している。「結局、それを実行したのは彼らだが、望んだのは私たちのほうなのだ」と。22。
現代においてわれわれは準拠すべきオリジナルを失い、ツインタワーが相互に反射する永遠に絡め取られていたが、21世紀の始まりにそれすらを失った。地図も領土もなくなった帝国の終わりで、我々は電話ボックスにいる。
君たちのうち、いったい誰に永遠に生きる価値があるだろう?
ミシェル・ウエルベック「ある島の可能性」
- この説明は数学的対象の実在という更に厄介な議論を呼んでしまうのだが、まあ許していただきたい。何を言っているかわからないという人は、人々は「3のイデア」と「紙の上にインクで書かれた3」との間に区別をつけているか、という問題提起だと思ってもらえばよい。
- 現物の画像を貼れるとよかったのだが、それはできない。我が国におけるマグリットの著作権保護期間が戦時加算によって微妙に伸びているためだ。勝っておけばよかったな。
- 訳は筆者。
- これは後に紹介するボードリヤールの態度とも共通している。
- 「それが示す領土ではなく別の場所に置けばいいのではないか」と思われた方もいるだろうが、たとえば極端な場合として宇宙全体の縮尺1/1地図(!)を考えるとそうもいかないことがわかる。
- この話はスアレス・ミランダなる人物の手になるとされているが、いつもどおりボルヘスじしんの創作であろう。
- 帝国の地図(縮尺1/1)、河出文庫「ウンベルト・エーコの文体練習」所収。
- 「それ自体と領土の間に置かれたすべての地図を表示するがそれ自体は表示しない」地図。
- たとえば「この文は真である」は自己言及する文だが、何ら問題を生じない。
- <標準地図>には「それ自体を表示しない」という制限があるので、そこまでタチの悪い自己言及は発生しないのではないかと思う。
- Wikipedia「クワイン」より。
- たとえばLispはこのような性質を活用しやすい言語として有名である。リストも関数もS式として均質に扱える。
- 円城塔が(そしてこんなことを小説に書く人が)チャーチ・チューリングのテーゼを知らないわけがないし、「神父C」というのもチャーチを意識しているように思える。
- 菊池誠「不完全性定理」p146より。
- 理論上同等であるという話で、Turing機械で計算を遂行するのはかなりめんどうだが。
- Robin GandyはGandy MachineというTuring機械の一般化を考案し、この点に関して物理的制約による限界が存在することを示唆しているようで、事態はそれほど明るくはないのかもしれない。
- 「シミュラークルとシミュレーション」冒頭。
- さらに言えば、ウォーホルが描いた32個のトマトスープ缶のうち、どれかが本物だということが果たしてあるだろうか?
- 「ロボット」はチャペックの造語だが、チェコ語のrobota(賦役、重労働)やスロバキア語のrobotnik(労働者)が語源になっているという。
- ボードリヤール本人はこの映画をあまり好んでいないらしいが。
- もちろん訓練を積んだ人間なら解読できるだろうが、ここでボードリヤールはDNAを人体に埋め込まれたブラックボックスであり、人間はそれに関与できないが生体が解釈するものに見立てている。
- 「テロリズムの精神」より。益体もない註釈だが、これはテロリズムの単純な肯定として解されるべきではなく、グローバリゼーションの自壊と関連付けられるべきである。



